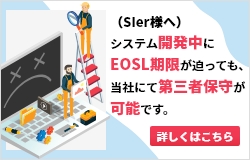【法人向け】EOSL後もシステムを使い続けたい担当者様へ。日米保守事情の違いから学ぶ。

~部品流通・保守・利用者の考え方~
コンピューターの部品がEOSL(End of Service Life=メーカー保守終了)を迎えると、企業のIT担当者は対応に悩むことが少なくありません。ここでは、日本と米国におけるEOSL後の事情を比較してみます。
1. 保守部品の流通
日本では、EOSLを迎えるとメーカー正規部品の供給が途絶えやすく、中古市場の規模も小さいため入手は困難になります。
一方、米国ではEOSLになった再生部品の流通網や独立系保守ベンダーが充実しており、EOSL後も比較的容易に部品が手に入ります。
2. 部品を交換する人
日本ではメーカー技術者に依存する傾向が強く、EOSL後に自ら交換するケースは少なめです。米国ではユーザー自身が部品を調達・交換したり、第三者保守のエンジニアに依頼するケースが一般的です。
3. EOSL部品の保証と信頼性
EOSL部品はメーカー保証が切れているため、日本では「保証がないなら更新すべき」という判断につながりやすいです。米国ではワランティーに代わり、サードパーティが独自に保証をつけて販売することも多く、実用面での信頼性を担保しています。
当社の場合、出荷される多くの部品に、180日の保証をお付けしています。
4. コンピューター担当の考え方
日本の担当者は「壊れたら買い替え」志向が強いのに対し、米国では「壊れたら直して延命」という姿勢が根付いています。結果として、日本では更新サイクルが早く、米国では延命ビジネスが大きく育っています。
5. まとめ
EOSL後の対応は、国ごとに文化や市場構造の違いが表れます。日本では更新を選ぶ企業が多い一方、米国では延命のための選択肢が豊富です。今後、日本企業もコスト最適化の観点から「第三者保守」という選択肢を検討する流れが加速するかもしれません。
当社は、第三者保守の会社です。お手伝いできることがあると思います。悩む前にお気軽にお声がけください。
EOSL製品の延命ならへお任せください
お電話・FAXでのお問い合わせ
- 03-5259-6065
- 03-5259-6066



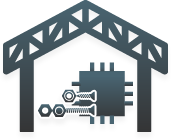
![[修理事例] Fujitsu FMV D5245 常時電源オンで使用しているが、ある日電源オフになっていた。](https://www.3scom.jp/dcms_media/image/blog_repair.png)
![[パーツ・システム販売] DAT72テープドライブを動かしてみた 〜Sun Blade 2500で検証〜](https://www.3scom.jp/dcms_media/image/blog_selling.png)